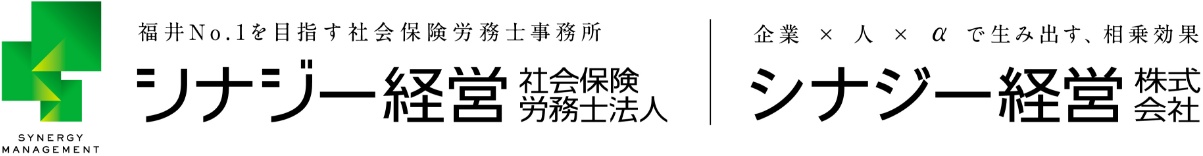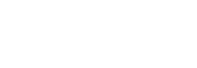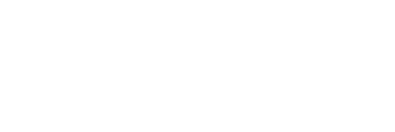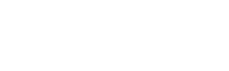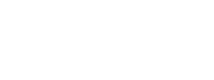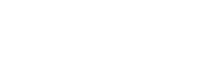賞与の月給化の効果は?
冬の賞与の査定に向けて
面談を始めている企業も
多いと思います。
賃上げやインフレ対策の
ひとつとして賞与を給与に
組み込み、月額の給与を増加
させる、いわゆる
「賞与の月給化」★が
(退職金の月給化も同様)
大手企業を中心に導入されていますが、
実際の所、効果はどうなんでしょうか。
★賞与割合を減らして、月給に組み込む
パーソル総合研究所が
「賃上げと就業意識に関する定量調査」
を公表しその中に賞与を月給に組み込む
ことの調査結果を発表しました。
賃上げとモチベーションについて、
「ベースアップ」があっても半数は
モチベーションが高まらず」
自社でベースアップがあった人のうち、
モチベーションが向上したのは約半数に
とどまりました。
年代別に見ると、ベースアップで
モチベーションが向上した人の割合は、
20代で6割弱。年代が高いほど、
モチベーションが向上した人の割合が低く、
自社でベースアップがあっても半数以上は
モチベーション向上につながっていない。
という結果でした。
グラフを見ると、20代・30代は歓迎、
40代以上は後ろ向きというような
傾向です。
一部声を拾ってみると、
・「退職金の月給化を実施してほしい」
(25歳男性,教育・学習支援業)
・「賞与の月給への組み込みを
しているだけで、総額年収は変わらない。
40代以上はベースアップの恩恵がなく、
20-30代と経営層のみ年収が上がっており、
やる気が出ない」(44歳男性,製造業)
・「賞与を月給に組み込むことで、
業績を反映した賞与に期待できなくなる」
(51歳女性,宿泊・飲食サービス業)
・「退職金制度がなくなったのが不安」
(31歳女性,金融・保険業)
社員の年齢層にもよるため
これが最適というのはなかなか
難しいですが、
報告書には、離職防止には
他社との横並び(ヨコ比較)ではなく、
「給与の未来展望」(タテ比較)を示すことが
鍵であると提言しており、
賞与の一部を月例給与に組み込むことが
「未来の安定性」の手段となることも
記載されています。
1.将来不安の直接的な軽減
賞与は業績連動性が高いため、将来の変動リスクが
あります。対して、月例給与を安定的に底上げ
することで、従業員は「毎月の生活が支えられる」
という確かな安心感を得られます。
これは、「給与が変わらない」ことによる
離職リスクを直接的に解消する力もあります。
→月額給与が上がることで社会保険料のアップ
も想定されますので、導入の際には
シミュレーションが必要です。
2.納得性・透明際の担保
継続就業意向を高める要素として、
給与の「調整方針の透明性」や
「決定方針の透明性」といった
「納得性」が非常に重要です。
賞与の一部を固定的な月例給与に
移管することで、従業員は自分の
労働対価がより明確になり、
給与体系に対する納得感と信頼感が
向上します。
→人事評価制度の導入は不可欠でしょう。
3.育成意欲の維持
自身と部下・後輩との給与差の縮小や、
将来の昇給期待の喪失が、上司・先輩層の
育成意欲を低下させている点も懸念
されています。
月例給与の安定的な上昇カーブを示すことは、
中堅・ベテラン層に対し、
「自分自身の未来も明るい」
という確信を与え、
結果として組織全体の育成力を
維持・向上させる効果が期待できます。
→中堅・ベテラン社員にも1on1などで
意思疎通を図っておく必要があります。
賞与を月給に組み込むことは
ひとつの方法であり、
見せ方についても効果がありますが、
企業の戦略となりそうです。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社